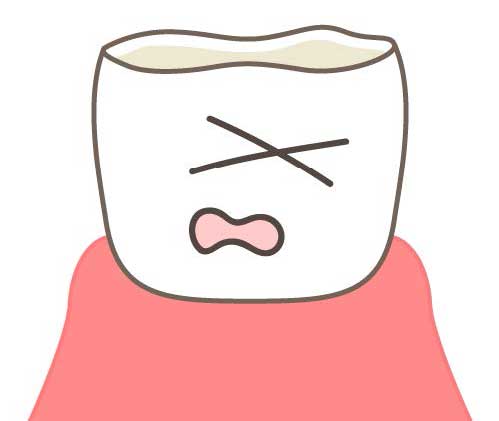2025年10月23日

渋谷歯医者矯正歯科の澤田尚哉です。
本日のブログのテーマは『矯正治療の必需品。顎間ゴムって?渋谷の歯科医が解説!』です。
矯正治療中に「顎間ゴム(がっかんゴム)をつけてください」と言われたことはありませんか?
「小さいゴムを毎日つけるなんて面倒…」「どんな意味があるの?」と感じる方も多いのではないでしょうか。
実はこの顎間ゴム、矯正治療の“仕上がり”を左右する非常に重要なアイテムなんです。
今回は、渋谷の歯医者が顎間ゴムの役割・種類・重要性を分かりやすく解説します。
顎間ゴムとは?

顎間ゴムとは、矯正装置に小さなゴムをかけて、上下の歯の位置関係(かみ合わせ)を整えるための補助器具です。
英語では「エラスティック(Elastics)」と呼ばれ、主にワイヤー矯正やマウスピース矯正の噛み合わせの調整などで使われます。
矯正装置だけでは「歯を動かすこと」はできても、「上下の噛み合わせ」を細かくコントロールするのは難しいため、このゴムの“引っ張る力”を利用して上下のバランスを調整していきます。
顎間ゴムの目的
顎間ゴムの最大の目的は、上下の歯を正しい位置で噛み合わせることです。
矯正中は歯が並んでも、噛み合わせがずれていると機能的にも審美的にも中途半端な状態になってしまいます。
ゴムを使うことで次のような効果が得られます
・出っ歯(上顎前突)の改善
・受け口(下顎前突)の改善
・左右のずれの補正
・奥歯のかみ合わせ調整
顎間ゴムは“歯並びを整える”だけでなく、「しっかり噛める美しいかみ合わせを作る」ための最終調整ツールです。
顎間ゴムの種類
顎間ゴムには、かける位置や目的によっていくつか種類があります。
① Ⅱ級ゴム・クラスⅡエラスティック(出っ歯の矯正)

上の犬歯付近と下の奥歯をつなぐようにかけるタイプ。
上の歯を後方に、下の歯を前方に引っ張る力が働き、出っ歯(上顎前突)の改善に効果的です。
② Ⅲ級ゴム・クラスⅢエラスティック(受け口の矯正)

下の犬歯付近と上の奥歯をつなぐタイプ。
下の歯を後方に、上の歯を前方に動かし、受け口(下顎前突)の改善を行います。
③ 交叉ゴム・クロスエラスティック(交叉咬合の改善)
上下の歯の噛み合わせが左右にずれている場合や歯が内側に倒れており、上下の歯が噛んでいない場合に使用。
歯を斜め方向に引っ張ることで、左右差や傾きを補正します。
④ 垂直ゴム・垂直エラスティック(上下の隙間を閉じる)

上下の歯の間に隙間(開咬)がある場合に使用。
垂直方向に引っ張ることで、上下の歯を密着させて噛み合わせを安定させます。
顎間ゴムはどれくらい続けるの?
一般的には、1日20〜22時間の装着が目安です。
食事や歯磨きのとき以外は基本的に常時装着します。
1日の中で1〜2回交換してください。同じゴムを使い続けると、劣化などで力が半減してしまいます。
特に矯正の終盤では、ゴムをどれだけ真面目に使うかで治療の完成度が変わるといっても過言ではありません。
怠ると治療期間が延びたり、噛み合わせがずれたままになってしまうことも・・・
顎間ゴムをうまく使うコツ
✔ ゴムは毎日新しいものに交換する(伸びると効果が弱まる)
✔ 予備を常に持ち歩く(外食や外出時に便利)
✔ 食事・歯磨きの後はすぐにつけ直す
✔ ゴムの位置を間違えないよう鏡で確認する
最初は装着に慣れないかもしれませんが、1〜2週間ほどで違和感は少なくなります。
ゴムの正しい装着が「最後の仕上がり」を決めると思って頑張りましょう。
渋谷の矯正歯科での傾向
渋谷エリアでは、マウスピース矯正(インビザライン)にも顎間ゴムを併用するケースがほとんどです。
特に成人矯正では、噛み合わせや顎の位置を精密に整えるために重要な役割を担います。
「目立たない矯正をしたい」「短期間で効果を出したい」というニーズに応えるため、透明マウスピースと顎間ゴムを併用する矯正が主流になりつつあります。
まとめ|顎間ゴムは矯正の「最終仕上げ」
顎間ゴムは、上下の噛み合わせを整えるための重要な装置です。種類やサイズによって「出っ歯」「受け口」「左右のズレ」「開咬」などに対応しているため、主治医の先生の指示に従いましょう。
1日20時間以上の装着をし。1日の中で1〜2回交換が理想です。
サボると治療効果が下がり、期間が延びることも・・・
矯正治療を成功させるカギは「日々の継続」にあります。
小さなゴムですが、その積み重ねが理想の笑顔と正しい噛み合わせを作ります。
ぜひ矯正をされてる方は頑張りましょう!!